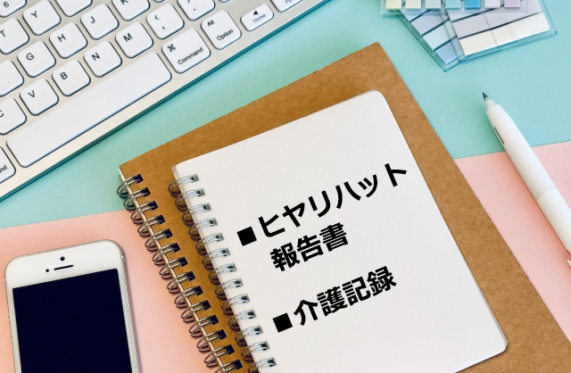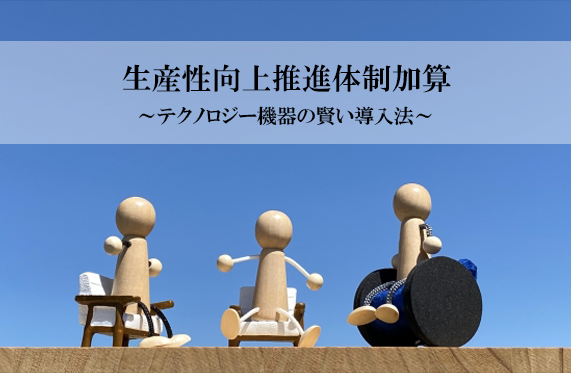ナースコールは介護スタッフにとって使い慣れているものですが、入居者にとっては「どのタイミングで押すのか?どこに向かって話すのか?」といった疑問も持つこともあります。また病気やケガ、障害などでボタンを押せないケースもあります。
今では見守りセンサーやスマートフォンに連携できるなど、豊富な機能が備わったナースコールも登場しているため、入居者と介護スタッフ双方が使いやすいナースコールを導入することが重要です。
この記事ではナースコールの基本的な使い方や、使いやすいナースコールについて解説します。
目次
入居者は、ナースコールの使い方を理解していますか?
ナースコールの基本的な使い方
ナースコールの種類別の仕組み
従来型ナースコール
電話主装置型ナースコール
PC管理型ナースコール
■入居者は、ナースコールの使い方を理解していますか?
ナースコールは介護スタッフにとっては使い慣れたツールです。しかしこれまでナースコールを利用する機会がなかった場合、いざ使おうとしても「どうやって使うのか?」「どこに向かって話すのか?」などの疑問が生じることもあります。そのため入居者に向けて、ナースコールの基本的な仕組みや呼び出す方法などをしっかりと説明することが大切です。
しかし実際には、ナースコールについて「必要なときにボタンを押してください」といった簡単な説明しかされていないケースがほとんどです。これでは入居者の疑問や不安につながり、適切にナースコールが使用されないリスクも出てきます。またナースコールはボタンを押すものや、離床センサーなどと連動して通知するものなど種類もさまざまあり、使用方法も異なります。
入居者が安心・安全な暮らしをするためにも、ナースコールの疑問や不安を解消し、正しい使い方ができるような説明が必要です。
■ナースコールの基本的な使い方
ナースコールの基本的な使い方は以下のとおりです。基本的な流れをしっかりと説明できるようにしておきましょう。
【ナースコールの使い方】
- 入居者がナースコールの子機にあたる呼び出しボタンを押します。
- スタッフルームに設置されたナースコールの親機やスタッフが携帯する端末(ナースコールと連携できるPHSやスマートフォン)に通知されます。
- スタッフは親機や端末から、入居者は子機をとおして、相互通話が可能です。必要に応じてナースコールの通知があった居室へと駆けつけます。
- 対応が完了したら、ナースコールの復旧ボタンを押すなどしてナースコール通知の解除を行います。
入居者が利用するナースコールの子機にもさまざまなタイプがあり、形状や使い方、通知される仕組みなどは異なります。ナースコールを導入する際は、入居者の使いやすさや介護レベルに応じたもの、目的にあわせたものを選ぶ必要があります。おもなタイプとそれぞれの特徴の違いを知っておきましょう。

【ナースコールの子機のタイプ】
- 据え置き型
各居室に取り付けるタイプのナースコールです。ベッドサイドに取り付けることが多く、ナースコールのなかでも代表的なタイプです。スタッフと通話できる点が特徴です。
- 携帯型
携帯型のナースコールは壁などに固定する必要がなく、自由に持ち運びが可能です。電波が届く範囲であれば、ベッドにいなくてもどこからでもスタッフを呼び出せます。首からかけられるタイプなど、持ち運びしやすい形状になっているものが多数あります。
- センサー型
身体の動きなどをセンサーが感知して、スタッフに通知するタイプです。手をかざすだけで反応するものや、ベッドからの起床や離床で反応するものなどさまざまなタイプがあります。ナースコールのボタンを押せない方や、転倒・転落・徘徊リスクのある方などに使用されることが多いです。
ナースコールに慣れていない入居者が疑問や不安を感じないように、しっかりと説明しておくことが大切です。また呼び出しボタンをベットサイドに設置するものや持ち運べるもの、センサーによって通知するものまで幅広くあるため、入居者の状況にあわせたものを選ぶことが使いやすさにつながります。
■ナースコールの種類別の仕組み
ナースコールのシステムは、大きく分けて以下の3つがあります。仕組みが異なり、高規格なものや柔軟性が高いものなど、特徴の違いもあります。
従来型ナースコール
ナースコール専用の制御装置をメインに、親機や各居室の子機とつなぐ仕組みです。PBXとは連動できず、親機でのみ呼出の確認が出来ますが利便性の観点から旧式となっているタイプです。
電話主装置型ナースコール
ナースコールの制御装置とPBXを連携させることにより、PHSなど移動端末でナースコールを受信することが出来るようになり、PHSや固定電話とも内線が可能で今では最もポピュラーなナースコールの仕組みと言えます。従来型のナースコールと比べると拡張性が高く、呼び出しや通話の信頼性が高いことがメリットなナースコールです。
PC管理型ナースコール
ナースコールシステムをパソコンで管理するタイプのナースコールです。これまで有線だったナースコールを、ソフトウェアや無線機器などを使用することでワイヤレスでの制御が可能です。そのため配線工事のコストカットや、自由な居室レイアウトも実現できます。またスマートフォンやほかのシステムとの連携ができる、柔軟性の高さもメリットです。
介護施設ではどのタイプのナースコールが使いやすいのでしょうか?こちらの記事で、選び方のポイントも含めて解説していますので、ぜひチェックしてください!
関連記事 >>>介護施設で使うナースコールの選び方は?押さえたいポイントを解説