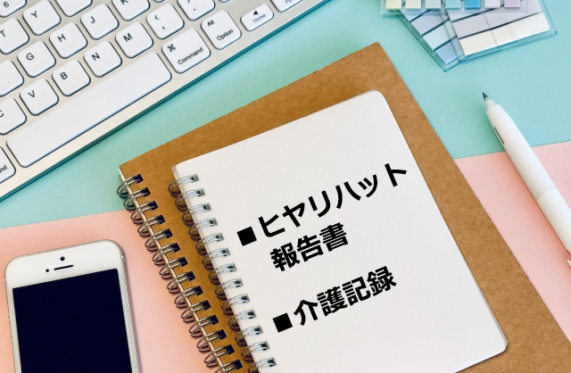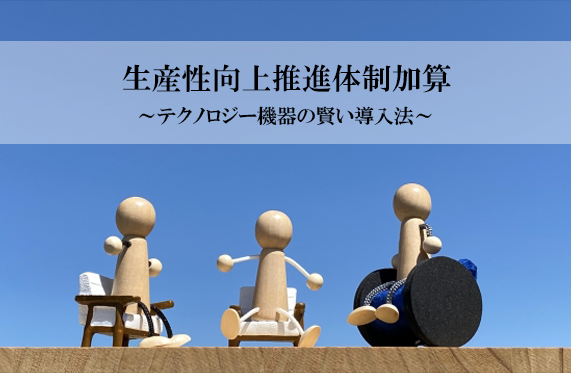介護施設において設置が義務づけられているナースコールですが、近年ではさまざまな機能が備わったものが登場しています。
ナースコールの「履歴機能」もその一つであり、うまく活用することでさまざまなリスクを防止し、業務の効率化やサービス品質向上へとつなげられます。この記事では、ナースコールの履歴機能の活用方法について解説します。
>>>関連記事 介護施設で使うナースコールの選び方は?ポイントを解説
目次
ナースコールの履歴機能とは?
ナースコールの履歴機能の仕組み
ナースコールの履歴機能の活用方法
頻回によるトラブルの対策
コール数のばらつきの把握ができる
ナースコールの頻回対策を行わない場合、どんなリスクがある?
入居者側のリスク
介護側のリスク
まとめ
■ナースコールの履歴機能とは?
ナースコールの履歴機能とは、ナースコールが押された際の情報を、後から振り返って確認できる機能です。ナースコールが押された日時や入居者の情報が集約され、「どの時間帯に呼出が多いのか?」「こちらの入居者は夜間に呼出が多い」など、ナースコールの傾向を把握できます。
ナースコール履歴のデータを振り返ることで、入居者ごとの注意点を把握したり、人員配置を見直したりなど、業務改善に活用できる機能です。

■ナースコールの履歴機能の仕組み
ナースコールが1回押されると、呼び出した入居者と時間、対応したスタッフや対応時間などの情報が、管理システムに保存されます。ナースコールが押される都度、これらの情報が管理システムへと蓄積されていく仕組みです。
履歴情報を確認する方法は、ナースコールのタイプによって異なります。たとえば居室ごとに録画・録音する映像付きのモデルだと居室別で履歴情報をさかのぼれたり、施設全体のデータから入居者別・日時別に自動でグラフ化できたりするモデルもあります。
またこのような確認機能がなくても、ナースコール情報を保存している管理パソコンからデータをCSV形式でダウンロードし、入居者別・時間帯別などでフィルターをかけてデータを分析するという方法もあります。
■ナースコールの履歴機能の活用方法
ナースコールの履歴情報を振り返ることで、以下のような問題の解決につながります。
頻回によるトラブルの対策
ナースコール履歴から、頻回に押されているのは「いつか・誰か」を確認し、なぜ頻回が発生しているのか原因を探れます。今まで感覚で捉えていたものが可視化されるため、正確な原因追及とその対策につながるでしょう。
ナースコールが頻回に押される状況は、本人やその家族から「スタッフがしっかり対応してくれない」などの不満につながる恐れや、頻回に押す入居者につきっきりになり他の方の対応が遅れるという問題も生じます。
このようなトラブルを避けるためにも、頻回なナースコールは改善しなければならない問題であり、履歴情報を確認して対策していかなければなりません。
コール数のばらつきの把握ができる
ナースコール履歴を分析することで、コール数のばらつきを把握できます。
たとえば「○階は呼出の多い方が複数人いる」ということがわかれば、スタッフの人員配置を見直して業務バランスを調整できます。また「朝方などに呼出が集中している」という分析ができれば、その時間は入居者のケア業務を中心に行うという判断も可能です。
フロアごとで呼出回数の多い・少ないの違いや、この時間帯はナースコールが集中しやすいなどの情報を可視化でき、業務改善に役立つでしょう。

■ナースコールの頻回対策を行わない場合、どんなリスクがある?
ナースコールの頻回対策を行わなければ、どのようなリスクにつながるのでしょうか。入居者側と介護側のそれぞれのリスクについて紹介します。
入居者側のリスク
ナースコールの頻回を放置していると、転倒や急変などの対応が遅れてしまうリスクがあります。
たとえばナースコールを頻回に押す人がいると、スタッフは「いつものナースコール」という心理が働いてしまうかもしれません。少しの油断につながり、実は急変を起こしていたのに対応が遅れてしまったという事態につながる恐れがあります。
またナースコールが頻回になる状況は、介護スタッフが対応に追われている状態です。遠慮がちな入居者だとナースコールを控えてしまい、満足な介護サービスを受けられないかもしれません。またスタッフを待ちきれずに自分で動こうとして、転倒してしまうという恐れもあるでしょう。
頻回を放置することで、サービス品質の低下につながり、入居者の安全性も失われてしまいます。

介護側のリスク
ナースコールが頻回に続くと、介護スタッフの業務量は当然のことながら増え、その他の業務は非効率的になってしまいます。
介護業務の内容は介護サービスだけでなく、ケアの記録やレクリエーションの準備など多岐に渡ります。なにか作業中にナースコールが鳴ると、中断して対応にあたることになり、戻った後に途中からやり直さなければなりません。
大きな施設だと、居室ごとの移動だけでも大きな負担となるでしょう。このようにもともとやらなければならない業務に加え、頻回なナースコールによって業務が円滑に回らなくなってしまうのです。
業務に追われて焦ったり思うように傾聴できなかったりしてしまい、十分なサービスを提供できないことから、スタッフが罪悪感を抱える恐れもあります。入居者への対応が遅れるなどのサービス品質につながることはもちろん、スタッフにとっても精神的なストレスを抱える原因となります。

■まとめ
ナースコールの履歴を確認することで、これまで感覚でしか把握できていなかった状況を可視化し、具体的な業務改善につなげられます。ナースコールが押される傾向を把握・分析すれば、適切な人員配置を行い業務改善につなげられるでしょう。
また入居者の傾向を知ることで、先回りケアが可能となり、効率的な作業にもつながります。頻回なナースコールに困っている場合にも、ナースコール履歴機能の活用が有効です。
ナースコールは履歴機能のほかにも、介護記録ソフトと連動でき業務効率化につながるものや、映像やセンサーを活用して見守りを強化できるものなど、さまざまな機能が登場しています。
履歴機能をはじめ、ナースコールの機能を活用して現場の改善を図りたい方や、ナースコールの導入や入れ替えを考えている方は、ぜひ一度ジーコムまでお問い合わせください。