介護施設ではスタッフが気づかないうちに、入居者が「離設」してしまう問題があります。離設すると事故や行方不明につながる危険があり、施設側の責任問題にも発展する恐れがあるため、しっかりと対策しておかなければなりません。
この記事では、介護施設における離設について、原因や予防策について解説します。
目次
■そもそも離設とは?
■介護施設から離設してしまう理由
認知症など病気が原因
心理的な要因
環境的な要因
■介護施設から離設しやすいケース
■介護施設の離設を予防する方法
過ごしやすい環境作りをする
心理的なサポートを行う
入居者の情報共有を行う
離設しにくい環境作りをする
センサーなど安全管理機器を設置する
■介護施設における離設への備え
緊急時の仕組み作りをしておく
入居者の写真を管理しておく
周辺地図を準備しておく
■介護施設の離設対策にはジーコムの製品がおすすめ
ココヘルパX
ココヘルパVP
共通センサー
■まとめ
■そもそも離設とは?
介護施設の「離設(りせつ)」とは、入居者が無断で施設外に出てしまうことです。自立した生活が難しく、見守りが必要な高齢者が多く入居する介護施設にとっての「離設」は、事故として扱われます。
離設が起これば、交通事故に遭ったり行方不明になったりしてしまい、最悪の場合は凍死や溺死などにつながるケースもあります。実際に離設して亡くなり、施設側が賠償責任を問われた事例もあります。
介護施設における離設は、入居者の命が危険にさらされる事態であり、介護施設の責任問題となる重大な問題です。そのため離設を防ぐための対策を、十分に行っていかなければなりません。

■介護施設から離設してしまう理由
なぜ入居者は、介護施設から離設してしまうのでしょうか。その原因は大きく分けると3つあります。
認知症など病気が原因
離設の原因は、認知症などの病気が大きく関係しています。認知症は、脳の神経細胞の働きが徐々に変化する病気であり、認知機能や記憶機能などが低下して、日常生活にさまざまな支障が出ます。
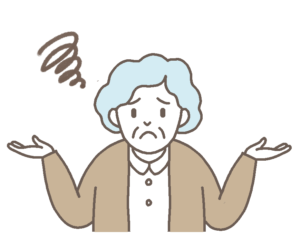
認知症の症状の一つに徘徊があります。徘徊はただウロウロと歩き回っているだけのように見えますが、どこかに行こうとしていたり何かを探したりと目的を持っていることが多いです。しかしその目的自体を忘れてしまったり、慣れているはずの道がわからなくなったりしてしまい、歩き続けてしまうことがあります。そうして施設内でウロウロと歩き始めた方が、施設外へ出るという事態が起こってしまうのです。
心理的な要因
入居者が抱える、さまざまなストレスや孤独などの心理的な要因も、離設の理由として挙げられます。
入居者は慣れない環境で生活し、スタッフや他の入居者などと接しながら生活を送るため、ストレスや不安などを感じることがあります。また家族と離れて暮らすことがつらく孤独を感じたり、これまでの日課を思い出して焦燥感にかられたりする方も少なくありません。
さまざまな心理的要因から「ここにはいたくない」「自宅に帰りたい」という気持ちが強まって、無断で施設を出てしまうことがあります。
環境的な要因
設備面やスタッフのケアなどの、環境的な要因が影響することもあります。
たとえば非常口のドアが開きっぱなし、窓や柵などの設備が劣化している、窓やベランダ近くに踏み台になるものが置かれているなど、物理的に離設を可能にしてしまうような管理はリスクが高まります。
またスタッフのケアにも注意が必要です。たとえば徘徊を防ごうとして入居者を拘束したり、居室にカギをかけたりするような行為です。このような不適切な介護は虐待にあたるうえ、抑制することで、より一層ここから離れたいと感じさせてしまいます。
■介護施設から離設しやすいケース
離設しやすい方のケースを見てみましょう。
- 徘徊癖がある
認知症の方のなかでもとくに徘徊癖がある場合は、十分な見守りが必要です。
- 帰宅願望がある
帰宅願望は認知症の方や、介護に抵抗を感じている方に見られます。「家族が家で待っている」「家に帰りたい」と訴える場合は、とくに注意が必要です。
- 入居して間もない
離設する方の多くは、入居して1年未満の方といわれています。入居後すぐは、これまで住んでいた家や家族から離れ、生活環境に大きな変化があることから、ストレスや不安につながりやすい時期だといえます。
施設での生活に慣れていなかったり介護に不満があったりすると、ストレスや不安につながり、「家に帰りたい」「ここにいたくない」と感じやすくなります。
■介護施設の離設を予防する方法
介護施設から入居者が離設することを防ぐためには、5つの予防策があります。

①過ごしやすい環境作りをする
まずは入居者にとって過ごしやすい環境を作ることが大切です。何もすることがなかったり、周りに話を聞いてもらえなかったりすると、孤独や不安を感じ、ここにいたくないという思いにつながります。
反対に、集中して取り組める作業や楽しめる趣味などがあると、心も満たされて暮らしの満足感が高まります。趣味を楽しめる環境を作ったりちょっとした作業をお願いしたりすることで、不安や孤独感を取り除き、自身の居場所であると感じてもらえるようになります。
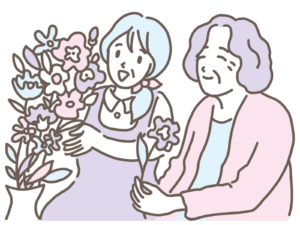
②心理的なサポートを行う
入居者の心理的なサポートも、離設防止につながります。
入居者が「ここにいたくない」「家に帰りたい」などの訴えがあれば、しっかりと傾聴して不安の原因を探ることが大切です。入居者の気持ちに寄り添いながら話を聞くことで、不安が解消されたりスタッフへの信頼感が高まったりし、過ごしやすい環境へとつながります。また趣味や好きなことなどに話題を変えて、楽しんでもらうことも有効な方法です。
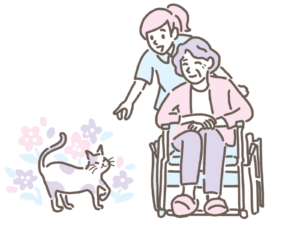
訴えに耳を傾けず、「帰れませんよ」「お迎えは来ません」などと、帰宅願望を否定するような声掛けはいけません。ますます不安をあおり、スタッフへの信頼も失われてしまううえに、不適切なケアにつながる恐れもあります。
③入居者の情報共有を行う
入居者の心理状態や様子は、スタッフ全員で把握することが大切です。「家に帰りたい」という訴えや徘徊癖はもちろん、日頃の様子や発言についてスタッフ間で情報共有します。普段から入居者をよく観察して、不安そうな様子や落ち着かない時間帯などの情報を、察知できるようにしておくとよいでしょう。
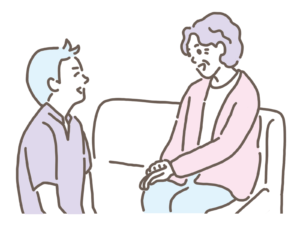
④離設しにくい環境作りをする
離設を予防するには、施設の環境づくりが必要不可欠です。玄関や非常口の施錠管理はもちろん大切ですが、あらゆる可能性を考慮したルール作りが必要です。
たとえば窓から外に出てしまわないように、窓の近くに踏み台になるようなベッドや棚を置かないようにしたり、玄関から出てしまわないように来客対応時のドア開閉にも注意したりというような工夫が大切です。
⑤センサーなど安全管理機器を設置する
スタッフだけで入居者全員をずっと見守ることには限界があります。気づかないうちに離設してしまうことを防ぐためには、玄関や廊下などにセンサーを設置し、ドアを開閉したり通行したりするとアラームが通知されるようにしておくと安心です。瞬時にスタッフが察知できるため、迅速な対応ができるようになります。
関連記事>>>介護施設で重要な「見守り」活用できるシステムや注意点を解説!
■介護施設における離設への備え
さまざまな離設予防を行っても、完全に防げるとは限りません。万が一離設が起こった場合に備えておくことも大切です。
緊急時の仕組み作りをしておく
離設が起こった際の対応方法について、決めておきましょう。その際は、以下のポイントにも注意してください。
上司や家族へ報告するタイミング、警察へ捜索願を出すタイミング、施設内・外の捜索方法などマニュアル化し、スタッフ全員で共有しておくことが大切です。
入居者の写真を管理しておく
入居者を捜索するうえで、顔写真が必要となります。入居当日に、胸から上の写真と全身写真を撮影することを徹底し、管理しておきましょう。
周辺地図を準備しておく
周辺を捜索することになった場合に備えて、周辺地図を準備しておきましょう。捜索エリアをスムーズに分けられるように、あらかじめ幹線道路などや町単位で区切っておき、河川や踏切などの危険な箇所をマークしておきます。
そして即座に配布できるようにコピーをとっておき、マニュアルと一緒に保管しておくとよいでしょう。
■介護施設の離設対策にはジーコムの製品がおすすめ
入居者の離設を防ぐためには、入居者の不安やストレスの要因を取り除き、しっかりと見守り体制を整えておくことが大切です。これらを可能にし、離設対策に有効なのがジーコムの製品です。
ジーコムは、介護施設専用のナースコールシステム「ココヘルパ」シリーズや、さまざまなタイプのセンサーを開発・製造販売しています。
【ココヘルパX】
映像機能が付いたモデルの「ココヘルパX」は、インシデント発生時に後から映像を確認できるため、いついなくなったのかなどの事実確認が行えます。映像機能があることで虐待などの不適切な介護を抑止し、入居者のストレス要因をなくすことにもつながるでしょう。
またココヘルパXは、多彩なセンサーによって、入居者の状態変化を自動で通知します。入居者の状態や動作などをスマートフォンから確認できるため、いち早く異常に気づけるようになります。
【ココヘルパVP】
ココヘルパVPもココヘルパXと同じく映像機能を備えており、インシデント発生時の対策や、不適切な介護の抑止に効果的です。また映像型活動検知アルゴリズムで、入居者の夜間の動きを自動的に分析・検出し、活動量が多く変化するとスタッフに通知します。夜間の巡回をサポートし、効率的な見守りにつながります。
【共通センサー】
ジーコムではナースコールシステムだけでなく、エリア内侵入、ドア開閉などの、さまざまなタイプのセンサーも取り扱っています。
- ドア開閉センサー(SW23D)
ドアに設置する専用のセンサーです。ドアの開閉を通知するため、玄関や居室、共有スペースなどのドアへ設置するとよいでしょう。
- 空間センサー(SW23K)
廊下や通路に設置する人感式の空間センサーです。エリア内に立ち入ると通知されるため、玄関先や非常口付近などへの設置が有効です。
■まとめ
介護施設では、認知症などの症状や心理的な要因によって、無断で施設外にでる「離設」が起こる問題があります。入居者が事故や行方不明に遭わないようにするために、離設対策が欠かせません。
入居者がここは自分の居場所であると感じ、安心して暮らしてもらえるような環境を作ることが大切ですが、センサーなどの機器を導入して物理的な対策を講じることも不可欠です。
離設対策として、見守り機器やセンサーなどの導入を考えるなら、ぜひジーコムまでお問合せください。
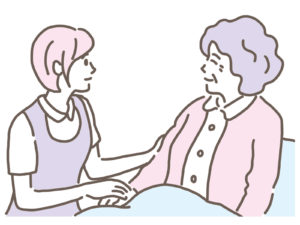
| 執筆 | ジーコム株式会社 プロモーション部 |











