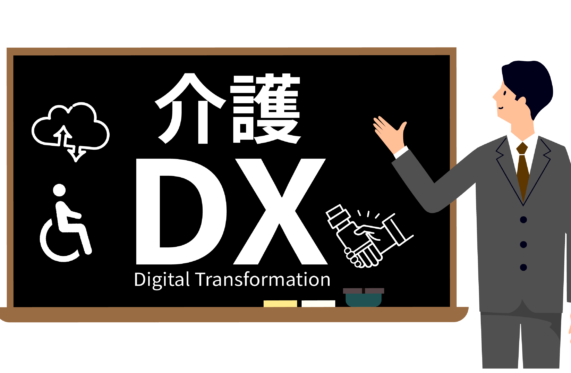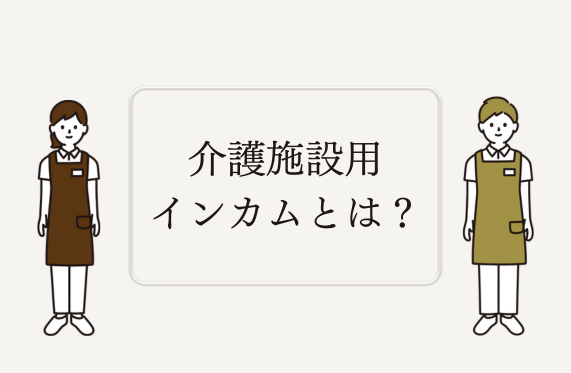多くの業界で加速しているDXですが、近年は介護業務でも同様にDXが進められています。積極的にDXに取り組む介護施設が増える一方で、「進め方がわからない」「コストや人材などの課題が気になる」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、介護DXの推進理由や課題を解説します。
目次
介護DXを推進させる理由
-人手不足の解消につながる
-業務負担を軽減させる
-サービス品質の向上ができる
-災害時の対応強化ができる
介護DXの課題
-導入コストが発生する
-DXに対応できる人材が必要
-セキュリティ対策やプライバシー保護が必要
介護DXとは?
介護DXとは、ICT機器やAI、ロボットなどのデジタル技術を活用して、介護業務のワークフローを変革する取り組みのことです。
そもそもDXとは、「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)」の略称です。Transformationは「変容」などの意味があることから、DXは「デジタル技術を活用することによる、ビジネスモデルや業務プロセス、組織文化などの変容」を意味します。

単にデジタル技術を導入するだけではなく、活用することによって業務やサービスなどの改善を図り、成果につなげるまでがDXです。
介護業界におけるDXは、介護業務を変革させることで、よりよい介護サービスの提供とスタッフが働きやすい職場を実現し、両者の満足度や生活の質の向上を目指す取り組みといえます。
介護DXを推進させる理由
人手不足の解消につながる
介護DXを推進させるもっとも大きな理由は、人手不足の解消のためです。少子高齢化に伴って、介護を必要とする高齢者が増える一方で、働く人口は減少しています。そのため介護業界では必要な人材をなかなか確保できず、慢性的な人手不足が問題となっているのです。
厚生労働省の調査によると、2026年度には約240万人の介護職員数が必要とされていますが、2022年度実績である約215万人と比較すると、約25万人が不足すると予測されています。また2040年度には、約57万人の介護職員数が不足するといわれています。
| 介護職員の必要数 | 不足数(2022年度比) | |
| 2026年度 | 約240万人 | 約25万人 |
| 2040年度 | 約272万人 | 約57万人 |
参考:厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」
この問題を解決する手段として期待されているのが、介護DXです。人材不足を補いながら、介護ニーズに応えるために、介護業務をサポートできるデジタル技術の活用が必要不可欠です。
業務負担を軽減させる
スタッフの業務負担を軽減できることも、介護DXを進める理由の一つです。介護業務は、肉体的にも精神的にも疲労を伴います。自力で生活が難しい方を常に見守りながら、食事や排泄、入浴などを介助し、体調の急変などに対応しなければならないケースもあります。また介助だけでなく介護記録をつけるなど、さまざまな事務作業なども発生するため、介護スタッフの業務負担は大きいといえます。
さらに慢性的な人材不足から、スタッフ一人ひとりの業務負担は増しており、長時間労働や夜勤、休日出勤などの増加にもつながっています。

介護DXを推進することで、これまで人の手でやっていた事務作業を削減したり、入居者の対応を効率化できたりします。時間や手間がかかっていた業務を、削減や効率化できることで、スタッフの負担軽減にもつながるのです。
サービス品質の向上ができる
介護DXは、介護サービスの品質向上にも必要です。介護DXの推進によって人手不足を解消し、業務負担を減らすことができれば、スタッフに余裕が生まれるでしょう。余剰の時間を入居者の直接的なサービスにあてたり、教育や研修にあて介護スキルをアップさせたりといった活用ができます。
またデジタル技術の活用によって、これまで以上に細やかなケアにもつながります。たとえば映像を活用することで、ナースコールの呼び出しがあれば居室の様子を確認し、状況を判断してから対応ができるようになります。無駄な訪室をなくし、迅速な対応につながるでしょう。
その他、居室で何かしらの動作があったときに、センサーが感知してスタッフに通知してくれるシステムを活用すれば、起床や離床にいち早く気付き、先回りのケアや転倒事故の防止なども期待できます。このように介護DXは、サービスの品質向上も期待できる取り組みです。
災害時の対応強化ができる
介護DXの推進は、災害時の対応を強化することにもつながります。
万が一災害が発生した場合、人の手だけで入居者全員の安否を確認するには、全居室へ訪室する必要があります。しかしセンサーやカメラなどのデジタル技術を活用すれば、入居者の状態をまとめて把握できるため、迅速な行動に移せるでしょう。
また入居者情報を紙書類で管理するのではなくデジタル化し、パソコンやスマートフォンなどの複数の端末からアクセスできるようにしておけば、事業所以外からでもすぐに情報へアクセスできるようになります。
緊急な対応や混乱が予想される災害時であっても、介護DXを推進しておくことで迅速な対応ができるため安心につながるでしょう。
介護DXの課題
人材不足を解消したりサービス品質を向上させたりするためにも、介護DXの推進が必要です。しかし介護DXに取り組むにあたって、いくつかの課題もあります。
導入コストが発生する
介護DXに向けて、デジタル機器の導入が必要不可欠です。ソフトウェアやシステムの導入費に加えて、設備や環境を整えるための工事費や、運用するための機器本体(パソコンやスマートフォンなど)の購入費がかかります。
介護施設の規模や導入するシステムなどによって費用は異なるものの、各施設にとって大きな投資となるでしょう。そのため費用を捻出することが難しく、導入に踏み切れないという施設も少なくありません。

しかし介護DXは、国としても推進されている取り組みであり、事業者が介護ロボットやICTなどのテクノロジーを導入する際の費用を補助する制度があります。このような制度を活用して、導入コストの負担を軽減することが有効です。
DXに対応できる人材が必要
介護現場にDXに対応できる人材がいないことも課題となっています。ITに精通した人材を確保することが難しく、なかなか進められないという施設も少なくありません。
またパソコンなどの機器操作に慣れていないスタッフにとっては、使いこなすまでに時間がかかり、デジタルの導入に抵抗を感じる場合もあります。従来の方法で対応できるのだから、わざわざ変える必要もないと思う人もいるでしょう。
そのため、DX人材の採用や教育を行って体制を整えていくこと、そしてスタッフにDX推進の流れや負担が軽減されることを説明し、理解してもらうことが必要です。
セキュリティ対策やプライバシー保護が必要
入居者の個人情報の管理には、セキュリティやプライバシーの問題が伴います。DXによって個人情報をデジタルで管理するようになれば、ウイルス感染・不正アクセスなどのサイバー攻撃や、人為的なミスによって情報漏洩のリスクが生じます。そのため強固なセキュリティが整ったシステムを導入することや、個人情報の取扱について意識を高めるスタッフ教育が必要です。
またセンサーやカメラの設置はプライバシーを侵害する恐れもあるため、最適な機器を選定することと適切な使用が求められます。

次回の記事では介護DXの取り込み手順、介護DXのサポートにつながる事例について詳しく解説していきます。