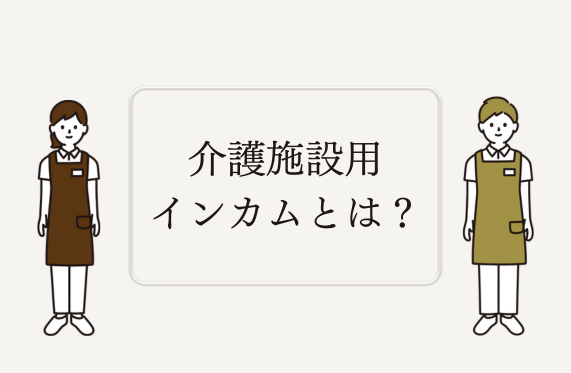前回に引き続き、多くの業界で加速しているDXについて解説します。
近年は介護業務でも同様にDXが進められています。積極的にDXに取り組む介護施設が増える一方で、「進め方がわからない」「コストや人材などの課題が気になる」という方も多いのではないでしょうか。
前回は介護現場の人手不足や課題について取り上げました。この記事では、介護DXの手順と取組事例をご紹介します。
関連記事>>>介護DXとは?推進させる理由と取り組むにあたる課題を徹底解説!
目次
1.目的と戦略を策定
2.推進体制を整備
3.課題の抽出
4.取り組みの優先順位の決定
5.ツールの導入・効果検証と改善
介護DXのサポートにつながる取り組み事例
介護DXにはココヘルパのナースコールがおすすめ
まとめ
■介護DXの取り組み手順
介護DXは、デジタル機器を導入するだけで進められるわけではありません。成果を出すためには、体制を整えたり課題を明確にしたりと、しっかりと準備をしておくことが大切です。ここでは介護DXの取り組み手順について紹介します。
1.目的と戦略を策定
まずは介護DXに取り組む目的と戦略の策定から進めましょう。何のためにDXに取り組むのか、どのような課題を解決したいか、目的を明らかにしたうえで、どのように取り組んでいくかの戦略を練っていきます。
DXは経営陣とスタッフを含めて、施設全体で取り組むべきものです。スタッフ一人ひとりが理解し、納得したうえで取り組めるようにするためにも、DX推進の目的や戦略をわかりやすく共有することが大切です。
スタッフが介護DXの全体像を把握できれば、前向きに取り組んでもらいやすくなるでしょう。
2.推進体制を整備
介護DXの取り組みは、施設全体で取り組むべきものです。経理陣から現場スタッフを含めたメンバーで、介護DXの推進体制を整備しましょう。

DXを推進するプロセスでは、業務プロセスの変更やコストの投入などの重要な稟議が何度も行われます。そのため決定権のあるトップが介入していなければ、スムーズに進められません。また実際に現場に携わるスタッフにも加わってもらうことで、スタッフの意向や入居者のニーズを反映できます。
3.課題の抽出
推進体制が整備できたら、次は課題の抽出です。現在の業務フローや使用しているツールなどから、施設全体の現状を把握します。現状を把握することで、負担になっている作業や解決すべき課題などが明らかになります。
課題の抽出と同時に、どのように解決すればよいか方法を検討していくことで、必要となる施策やシステムが具体化できます。

4.取り組みの優先順位の決定
課題が明確になれば、施策に取りかかります。しかし課題が一つだけとは限らず、複数の課題に一斉に取りかかるというのは現実的ではありません。
そのため取り組みの優先順位を決定させることが大切です。現場のニーズや緊急性、コスト、どれだけの効果が見込めるかを考慮したうえで、優先して取り組む課題を決めましょう。

5.ツールの導入・効果検証と改善
優先順位が決定したら、課題解決につながるツールの導入を進めます。新たなツールを導入する際は、機能性やコストだけにとらわれることなく、課題を解決できるかどうか、スタッフの使い勝手はどうかといった観点で選ぶことがポイントです。
またスタッフが抵抗感なくスムーズに使いこなせるように導入前の研修を行うことはもちろん、導入後もしっかりとサポートする体制を整えておきましょう。
そしてデジタル化が実行できれば、効果を検証することも忘れてはいけません。介護DXは、施策の効果が発揮され、サービス品質の向上やスタッフの負担軽減につながってはじめて達成されるものです。

そのため、どのような効果が得られたか、目的は達成できたかを検証することが大切です。問題がある場合は改善を図り、施策が完了すれば次の課題に取り組んで、施策の精度を上げていきましょう。
■介護DXのサポートにつながる取り組み事例
介護DXについてより深くイメージできるように、ここでは取り組み事例を一つ紹介します。
【取り組み事例:PHSからスマートフォンへの移行】

介護現場で連絡手段として使われてきたPHSですが、スマートフォンに移行した場合の活用方法やメリットなどを紹介します。
- さまざまなコミュニケーションができる
PHSは1対1の通話のみですが、スマートフォンなら複数人による通話やグループチャットなどができるため、さまざまな形のコミュニケーションがとれます。写真や動画も撮れるため、報告や情報共有などの資料としても活用できます。
- 居室の様子を確認できる
居室からナースコールでの呼び出しがあった場合、PHSなら居室の様子までは確認できませんが、スマートフォンなら映像と会話で状況確認が行えます。複数のナースコールがあっても優先順位をつけて対応にあたることや、必要なものを準備してから駆けつけられるため、迅速かつ効率的な対応ができます。
- 介護記録をその場でつけられる
スマートフォンを導入し介護記録ソフトと連動させることで、介助を行ったあとその場で介護記録をつけられます。これまでのように一旦メモしておいて、スタッフルームに戻ってから転記する必要はありません。記入漏れや二度手間を防止できるため、業務効率化につながるでしょう。またスマートフォンなら音声から文字入力もできるため、入力作業に手間取る心配もありません。

- 情報の確認や検索ができる
スマートフォンから介護記録システムの情報や、申し送りの内容を確認することも可能です。調べたいときに、すぐにその場で情報検索できる利点もあります。
- 翻訳アプリを活用できる
介護現場の人手不足を解消する手立てとして、外国人労働者の活用も有効な方法ですが、課題となるのが他言語でのコミュニケーションです。しかしスマートフォンなら翻訳アプリを使うことで、コミュニケーションもスムーズに行えるようになります。
- 必要な機能をプラスできる拡張性
スマートフォンは、さまざまなアプリを追加できる拡張性の高さが魅力です。今は必要なくても将来的に必要となったときにアプリを追加できるため、その都度機器を更新する必要はなくなり、長期的に使用できます。アプリが進化することでできることが増えていくため、さらなるサービス品質の向上や業務負担の軽減も期待できるでしょう。
■介護DXにはココヘルパのナースコールがおすすめ
介護DXを推進するなら、ココへルパがおすすめです。
ココヘルパは、介護施設で多く導入されている無線式ナースコールシステムです。シンプルな呼出機能のモデルから、介護DXにつながる最先端のモデルまで幅広く揃えています。
ほとんどのモデルがスマートフォンと連携できるため、上記で紹介した取り組み事例のように、さまざまなメリットがあります。
またココへルパは、他社の介護記録ソフトや見守りセンサーと連携できることも特長です。
すでに介護記録ソフトや、見守りセンサーを導入している施設も多いですが、これらの機器が連携できなければ、断続的な運用となってしまいDXにはつながりません。連絡手段のためだけのPHSや、見守りセンサーの通知を受け取るだけの機器の2台を持ち歩かないといけないことも負担です。
一方ココへルパであれば、スマートフォンや他社の介護記録ソフト、見守りセンサーと連携できるため、持ち歩きはスマートフォン1台のみですみ、シームレスな管理運用ができるようになります。単にデジタル化だけに終わらず、業務全体のDXにつながるでしょう。
■まとめ
介護DXを推進することで、介護業界が抱える人手不足の解消につながり、スタッフの負担軽減や介護サービス品質向上が目指せます。
DXを推進しようとデジタル機器を導入したとしても、断続的にしかできない管理運用ではDXとはいえないでしょう。しかしココへルパならそれぞれとの連携ができるため、効果を最大限に発揮できます。

介護DXを推進したい、さまざまな問題を解決したいと考えるなら、ぜひジーコムまでご相談ください。